「備え」を特別視しない——日常に溶け込む防災の本質
「災害」と聞くと、地震や台風、洪水、森林火災といった大規模なものを思い浮かべる人が多いでしょう。
しかし、私たちの日常の中にも「小さな災害」は無数に存在します。
たとえば、夫婦喧嘩や学校での言い合い、虫刺され、悪い夢。
人によっては、子育てだって「災害」と感じるかもしれません。
つまり、災害は一律のものではなく、それぞれの人生や状況によって異なるのです。
ここで重要なのは、「災害」と「日常」の間にこそ、本当の問題が潜んでいるということ。
防災というと、特別な準備や専門的な知識が必要だと考えがちですが、実はそうではありません。
むしろ、「災害」と「日常」の境界をなくすことこそが、本当の防災なのではないでしょうか。
「日常の延長」としての防災
被災地で暮らす人々の中には、「今の生活に慣れた」と言う人が少なくありません。
もちろん、慣れることがすべてではありませんが、「現実を受け入れ、自分にとって本当に大切なことを見極めること」が前進するための第一歩になります。
過去に執着しすぎると、なかなか次のステップへ進めません。
重要なのは、変化を受け入れながら、未来を具体的に描くことです。
変化と防災——本当に必要なものを見極める
人は、本質的に「楽で便利なもの」を求める生き物です。
たとえば、伝統的な和菓子が洋菓子の流行に押されて衰退しているのも、多くの人が新しいものを求めた結果です。
言葉は悪いですが、美味しいものを探す、美味しいと判断するよりも、流れてきた情報や誰かの判断に乗る方が楽です。
和菓子が美味しくて、洋菓子が美味しくないという話ではなく、人は忘れる生き物で、上書きされる情報が正になりやすいのです。
しかし、変化を受け入れながらも、自分にとって本当に必要なものを選ぶことが大切です。
個人的に、大きな変化を好むタイプではありませんし、キャンプ道具も、どんどんクラシカルなものに回帰しているように感じます。
ガスコンロやIHでは、こうはいきません。
共通するのは、「使いたい時に、使える環境があれば、いつでも使える」という点です。
新旧の区別ではなく、「使えるかどうか」が重要なのです。
そして今まで知らなかったものを知り、判断し、取り入れたものが新しかったり古かったりということで、実際に使ってみて使えるか使えないか判断しています。
知識としての「備え」——実体験の大切さ
 私たちにできるのは、「物理的な備え」だけではありません。
私たちにできるのは、「物理的な備え」だけではありません。
むしろ、それ以上に大切なのが、「知識的な備え」です。
「想像・創造的な備え」と言っても良いかもしれません。
その知識は実体験から得るのが一番です。
たとえば、我が子は、「燃える三要素=燃焼物・酸素・温度」を焚き火を通じて覚えました。
どうすれば火が消えるのか?
それを理解するには、実際に薪をくべながら試すのが一番の学びになります。
また、大人も子どもの「なんで?」という問いに向き合うことで、新たな気づきを得ることができます。
答えをすぐに与えるのではなく、一緒に考えることが大切なのです。
防災は「特別なこと」ではない
 多かれ少なかれ、私たちの人生には「災害」と呼べるものが存在します。
多かれ少なかれ、私たちの人生には「災害」と呼べるものが存在します。
しかし、防災を「特別なもの」として捉えるのではなく、日常の延長線上にあるものとして考えれば、より柔軟に備えることができます。
そのために重要なのは、「今の自分にとって本当に必要なものを見極めること」と、「実体験を通して知識を身につけること」です。
変化を受け入れながら、本当に使えるものを選び、知識を蓄えていく。
その積み重ねが、結果として「生き抜く力」になるのではないでしょうか。
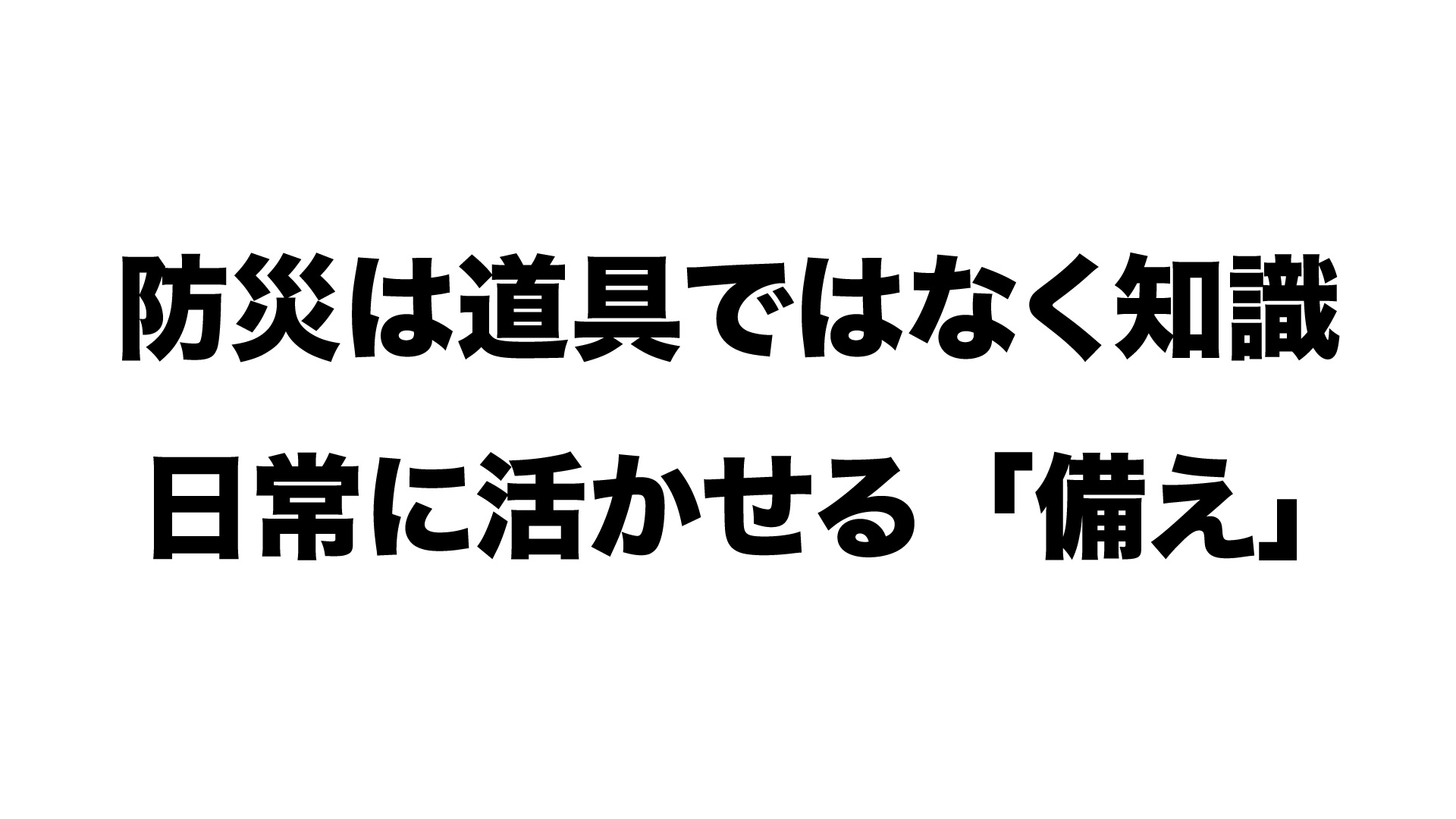


コメント