防災で本当に必要なものは「水」と「トイレ」? 実は語られない“命のインフラ”
 当サイトの防災関連のサイトのアクセスランキングを見るたびに感じるのは、「水」や「トイレ」への関心が非常に高いということ。
当サイトの防災関連のサイトのアクセスランキングを見るたびに感じるのは、「水」や「トイレ」への関心が非常に高いということ。
正直なところ、当サイトではあまり多く触れていないにもかかわらず、これほどまでに注目されているのはなぜなのかわかりません。
その理由を突き詰めていくと、人間の命に直結する「インフラ」としての重要性が浮き彫りになってきます。
特に当サイトは自助を目的で考えていると言うのもあるのかもしれません。
自助ができて共助、公助の恩恵に触れられるのですから。
食事よりも必要な水とトイレ
しかし、水がなければ3日と持たないのが現実です。
人間の体は約60%が水分でできており、それが失われることで命の危機に直結します。
日常的に当たり前に使っているこの存在も、1日に4〜5回は必要になるもの。
特に家族がいる場合は、衛生面やプライバシーをどう確保するかは非常に重要なテーマとなります。
水の確保は思っているより遥かに難しい
 では「水は備蓄すればいい」と考える方も多いかもしれません。
では「水は備蓄すればいい」と考える方も多いかもしれません。
実際、2Lのペットボトルを1人1日3本として7日分を用意すれば、1人あたり42Lが必要になります。4人家族なら168L。
これはなかなかの保管スペースが必要になります。
※現実的、実践的には「キャップ飲み」と言う技もあるので覚えておいた方が良いと思います。
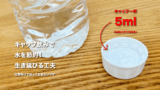
また、非常時に川や池などから浄水器で水を得るという発想もありますが、東京のような都市部では山水ではなく、工業排水なども混ざるため、簡易的なキャンプ用浄水器では除去しきれない化学物質が含まれていることも(要はゴミは取れるが、溶け込んだ水は濾せない)。
となると、都内で現実的な選択肢は「RO浄水器」や「蒸留水器」といった本格的な機器になります。
蒸留水器を導入して見えてきた現実
価格は当時から約4万円。
4Lの蒸留水を作るのに750Wで4〜6時間必要です。
つまり、電気が必要な蒸留では、非常時に実用レベルの水を確保するのは非常に難しいのです。
トイレの問題は「プライバシー」にある
家が無事で下水管も生きていれば問題ないですが、そうでない場合は仮設トイレや携帯トイレの出番となります。
ここで最も気になるのが「壁」です。
家族といえど、排泄の音やにおい、視線は極力避けたいもの。
プライバシーの確保は精神的な安定に直結します。
仮設テントで囲うという手もありますが、見た目以上に場所を取りますし、設置にもコツがいります。
耐風性能がありません。
最終的には見栄えなど気にしていられない状況になるかもしれませんが、やはり「気にしなくていい環境」が最初から整っているに越したことはありません。
消耗品から“耐久品”へ変わりゆく中で
 これまでの我が家の防災は「使い捨て」の消耗品が中心でした。
これまでの我が家の防災は「使い捨て」の消耗品が中心でした。
しかし、徐々に使い捨ての範囲を超えてくると「耐久品」に移行せざるを得ません。
ここでまた悩むのが、「失敗したら捨てるしかない」という点。
防災グッズ一つ選ぶにも、無駄にしたくないという気持ちが強くなり、つい先延ばしになってしまいます。
捨てるとなると粗大ゴミになりかねません。
ネットにはなんでも書いてあると言われますが、意外と書いてなかったりします。
これまではやれたけど、これからはなかなか難しい領域に入り、結果ブログの更新が滞ってくる。
調べるペースは何も変わっていないのですが。。。
答えはないが考え続けることが防災
 水とトイレの問題は、突き詰めれば突き詰めるほど難しくなっていきます。
水とトイレの問題は、突き詰めれば突き詰めるほど難しくなっていきます。
だからこそ簡単には語れませんし、逆に情報発信を避けてしまう人も多いのかもしれません。
ですが、この「悩み」や「不安」を共有することこそが、防災の第一歩になるのではないでしょうか。
どこまで備えるか、どんな方法を選ぶかは人それぞれ。
しかし、「今のままで本当にいいのか?」と問い続ける姿勢だけは、誰にでもできることです。
繰り返しで申し訳ありませんが、自助(0時間〜)があってこそ、共助(助け“合い”)や公助(72時間生き延びたら)が受けられます。
共助は理想であり、美しい姿ですが、近所の自販機のゴミの散乱や避難所の盗難のニュースを見るたびに幻想なんだと感じています。
相手を思う行動が共助のスタートですが、1ミリでも自分さえ良ければと思いがあったら壊れてしまう世界が共助なのだと思います。
ならばそれぞれが自力で生き延びようとする自助の集団である方が気が楽なのではないでしょうか?
相手に期待しても、期待されても、厳しい現代。
ならば自分のことは自分でやる。
最後の最後でどうしようもなくなった時にちょっと頼る。
現代は引っ越しそばを持ってお隣、近所にご挨拶なんて時代ではないと思います。
となったらどうすれば良いのか見えてくるのだと思います。
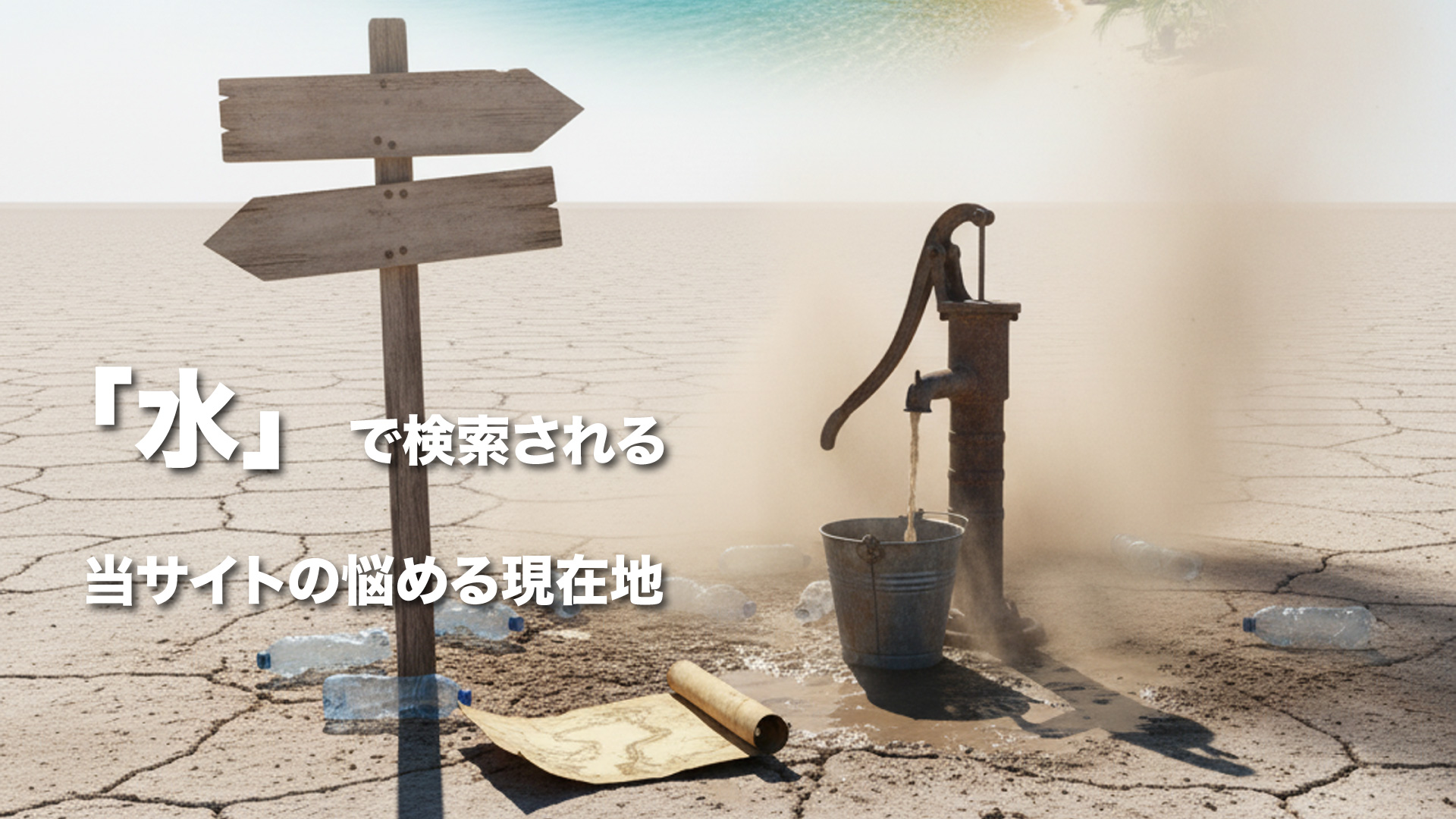


コメント