スマホがあれば安心。
災害時にも地図が見られるし、SNSで情報も取れる――そう信じていませんか?
でも、ちょっと待ってください。
その「安心」、本当に頼れますか?
本記事では、スマホに頼りすぎるリスクと、知っておくべき2つの事実について元電話屋が解説します。
災害時、スマホが「使えなくなる」2つの理由
理由①:トラフィック集中による回線パンク
 東日本大震災や各地の地震・台風でも報告された通信障害。
東日本大震災や各地の地震・台風でも報告された通信障害。
多くの人が一斉にSNSを使い、安否確認や情報共有をしようとした結果、回線がパンクして使えなくなる事例が相次ぎました。
しかもこれは、災害時に限った話ではありません。
大学入試の合格発表など、短時間のアクセス集中でもアクセス不能になることがあるのです。
つまり、いざというときにこそ「調べようとしても表示されない」「送ろうとしても送れない」ことが現実に起こっています。
理由②:目の前の現実より“どこかの誰か”を追いかけてしまう
 災害時、多くの人がSNSで情報を共有しようとします。
災害時、多くの人がSNSで情報を共有しようとします。
でもその情報、本当に“今”のあなたに必要なものでしょうか?
すぐ隣に困っている人がいるかもしれないのに、遠くの知らない誰かの投稿に気を取られる。
“情報を集めているつもり”が、実は問題から目を背けているだけになっていることもあります。
SNSで「困ってます」と呟く前に、あなたのすぐそばにいる人の声に耳を傾けてみませんか?
本当の備えは「スマホ」じゃない。「準備9割」の考え方
 昔、ご一緒した、あるテレビ局のディレクターがこう言いました。
昔、ご一緒した、あるテレビ局のディレクターがこう言いました。
「ないものは出てこない」。
つまり、自分の中にないものは絞り出そうとしても出てこないという意味です。
何も思っていないこと聞かれても本当に出てこないし、響かない。
また、私が20代で働いていた会社では、「準備が9割」という言葉が常に口ぐせのように飛び交っていました。
大体同じようなものです。
いざというとき、「自分の知識」「体験してきたこと」「身につけたスキル」が頼りになります。
防災の知識だけでなく、日常で得た人間関係や経験すべてが“生きる力”になるのです。
「災害時の沈黙」は、時に命を救う行動になる
 被災中、SNSの“善意の共有”が思わぬ混乱を生むことがあります。
被災中、SNSの“善意の共有”が思わぬ混乱を生むことがあります。
実際、デマや誤情報が拡散され、混乱を招いたケースは後を絶ちません。
だからこそ、
- SNSを使わない選択
- 無用な発信を控える判断
- 本当に必要な人のために帯域を空ける配慮
が、多くの命を救うことにつながるかもしれないのです。
災害時に本当に役立つスマホの使い方とは?
避難所の情報、安否確認、地図アプリ…。
でもそれも、スマホの電源が残っていればの話です。
災害直後は、むやみに使わず、
- 画面の明るさを最小にする
- 機内モード+Wi-Fiのみ使用
- 必要なときだけオンにする
など、バッテリーを守った方は遥に良いのです。
あなたの「沈黙」と「知識と経験」が命をつなぐ
むしろ百害あって一利なし、困難を生み出すツールになるかもしれません。
「繋がらない」「情報が出てこない」「充電できない」――そんな事態を想定して、今できることはただ一つ。
“スマホがなくても生きられる”準備をしておくこと。
災害時の行動は、平時の意識がすべてです。
今日から、“使い方”を見直してみませんか?
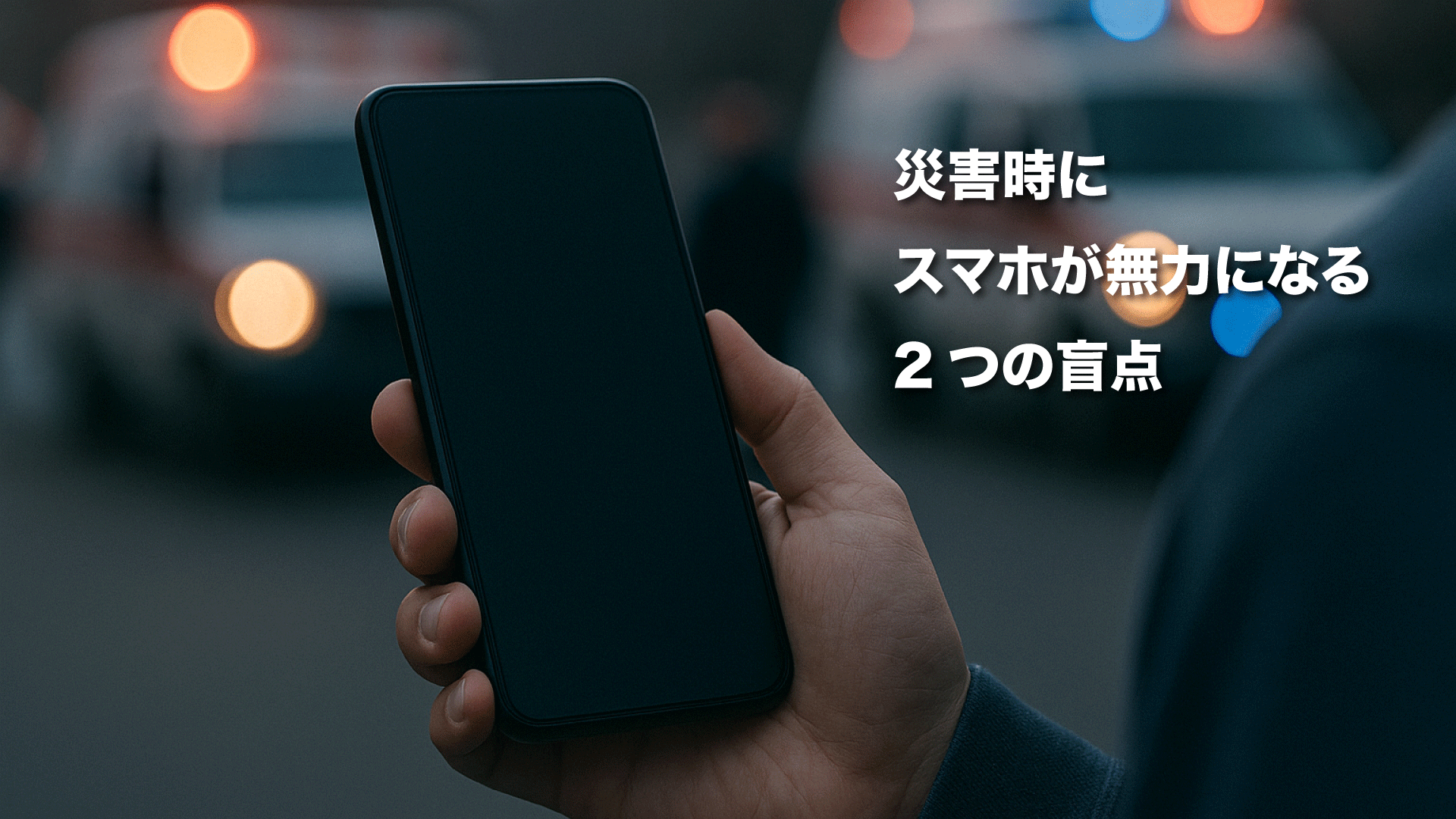


コメント