防災と子育ては、どこか似ている
 防災活動をしていると、ふと家庭のスタンスがにじみ出てくることがあります。
防災活動をしていると、ふと家庭のスタンスがにじみ出てくることがあります。
「備える」という行為は、単なる準備ではなく、“家の哲学”が問われる瞬間なのかもしれません。
我が家は「どうしたら?」の連続です
 我が家は自営業。
我が家は自営業。
子どもが生まれる前から「元々誰も必要としていないものをどう届けるか?」を問い続けてきました。
妻も同業なので、日常は「どうしたら?」という言葉のラリーが日常(ラリーという名の言い合い喧嘩?)。
子どもも自然とそこに巻き込まれて育ちます。
「どう思う?」という玉突き事故
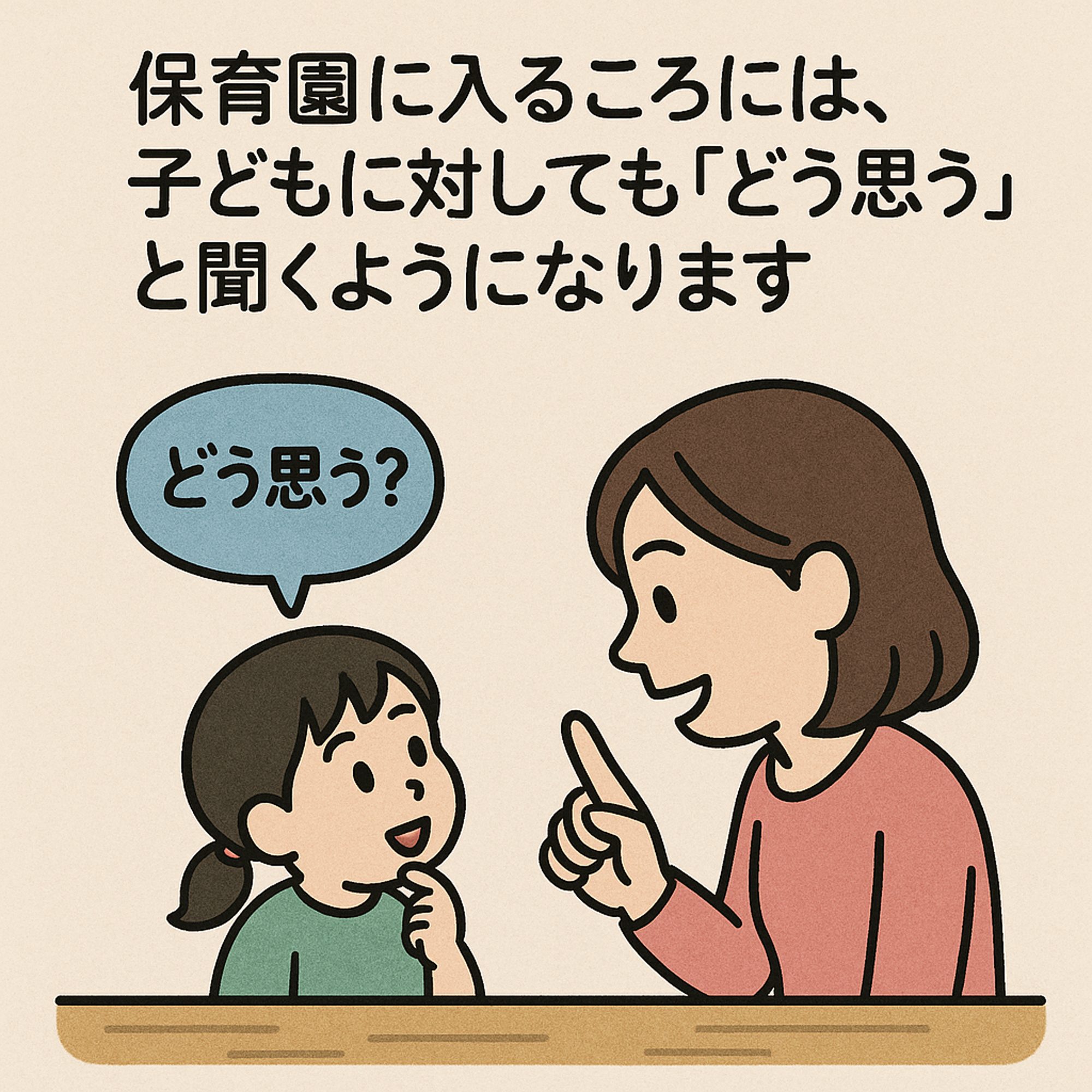 保育園に入るころには、子どもに対しても「どう思う?」と聞くようになります。
保育園に入るころには、子どもに対しても「どう思う?」と聞くようになります。
子どもの答えには“幼稚さ”というフィルターはかけない。
一人の意見として聞くと、時に“そもそも論”が飛び出してくる。
シンプルで自由なその発想が、私たちにヒントをくれることも。
我が家の“リアル・キッザニア”
 うちの子はキッザニアに興味がありません。
うちの子はキッザニアに興味がありません。
なぜか? すでに「ガチ」でやってしまったから。
- オーブンで焼き物を作る:ある意味日課、既に朝食は自分で作れる
- 消火器を実際に使う:防災館などで体験できますし、キャンプ場で消火訓練も(消化器じゃなくてもできる)。
- コピーライターとコピーについて考える:たまにこういう講座もあったりします
- 納品や仕入れに同行する:家に1人で置いておけないので
「挨拶しなさい」と言わなくても、私の行動を見て子どもは自然と頭を下げるようになります。
子育てで大事なのは「完璧」じゃなく「経験」
 すべてを理解しなくていい。
すべてを理解しなくていい。
でも、「どんなものか」を知っていればそれでいい。
親も完璧じゃない。だから子どもにだって“できない”があって当然。
ただ、“乗り越え方”だけは伝えてあげたい。
それがあれば、子どもは自分の力を発揮できると信じています。
日本の教育にも選択肢を
 ドイツでは10歳で職人か学者かを選ぶと聞きます。
ドイツでは10歳で職人か学者かを選ぶと聞きます。
それは極端でも、次のような制度があってもいいと思うのです。
✔️ 小学生高学年から選べる専門コース制度
- パン職人コース
- 消防士コース
- 美容師コース
- 文学コース
毎年、再選択できるようにすればいい。
ドイツの場合は早熟だけが評価されそうな感じになりがちだし、日本は大学に行っているのに仕事が決まらない現行制度よりも、選択させる考えるきっかけを何度も与えられる方がずっと健全です。
「悔しい」から「じゃあどうする?」へ
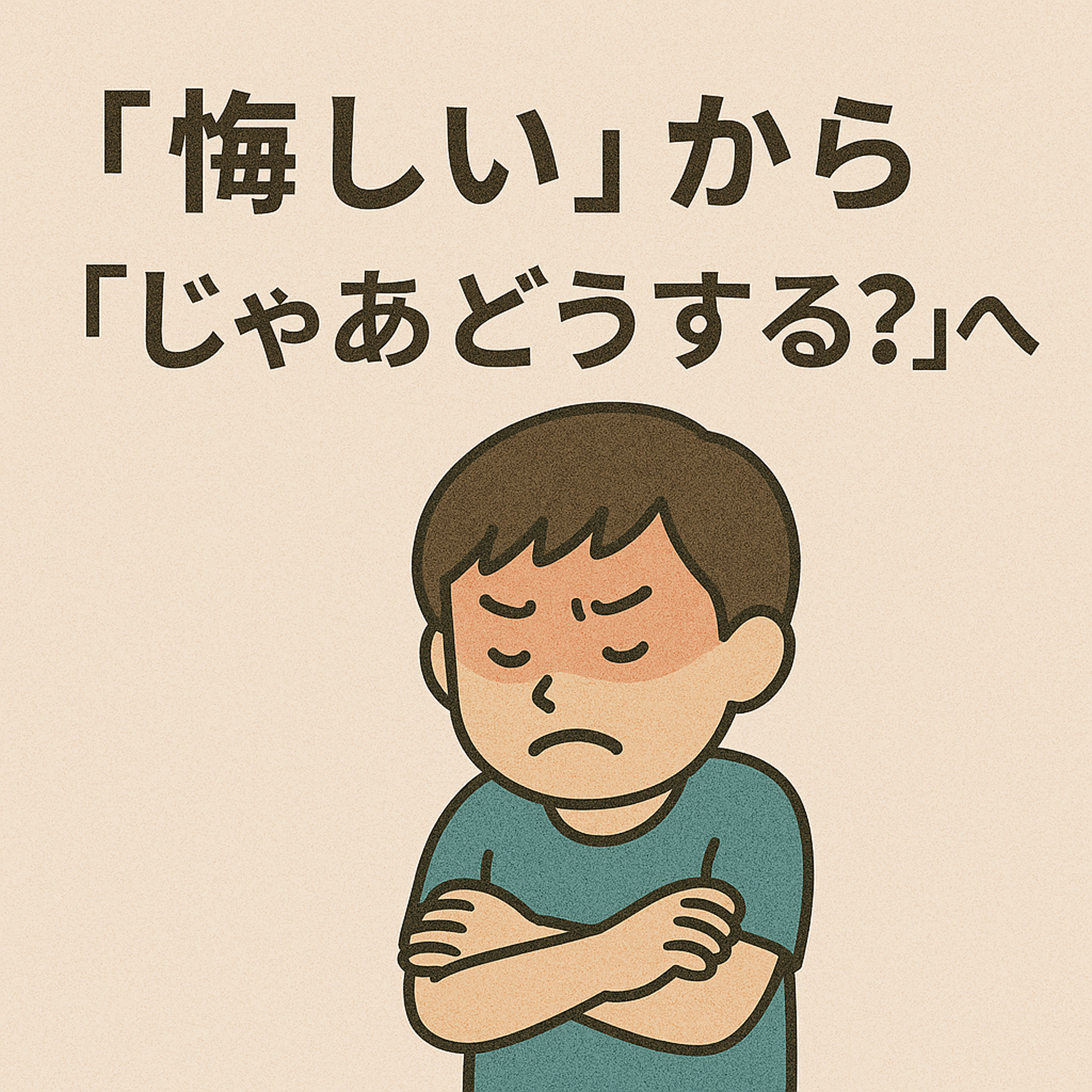 運動会で優劣をつけない最近の傾向。
運動会で優劣をつけない最近の傾向。
でもそれって本当に子どものため?
能力は違って当然。だからこそチャンスを与えることが平等なのでは。
勝ったら嬉しい、負けたら悔しい。
そこから「じゃあどうする?」が始まるのです。
防災も“命を守る学び”として
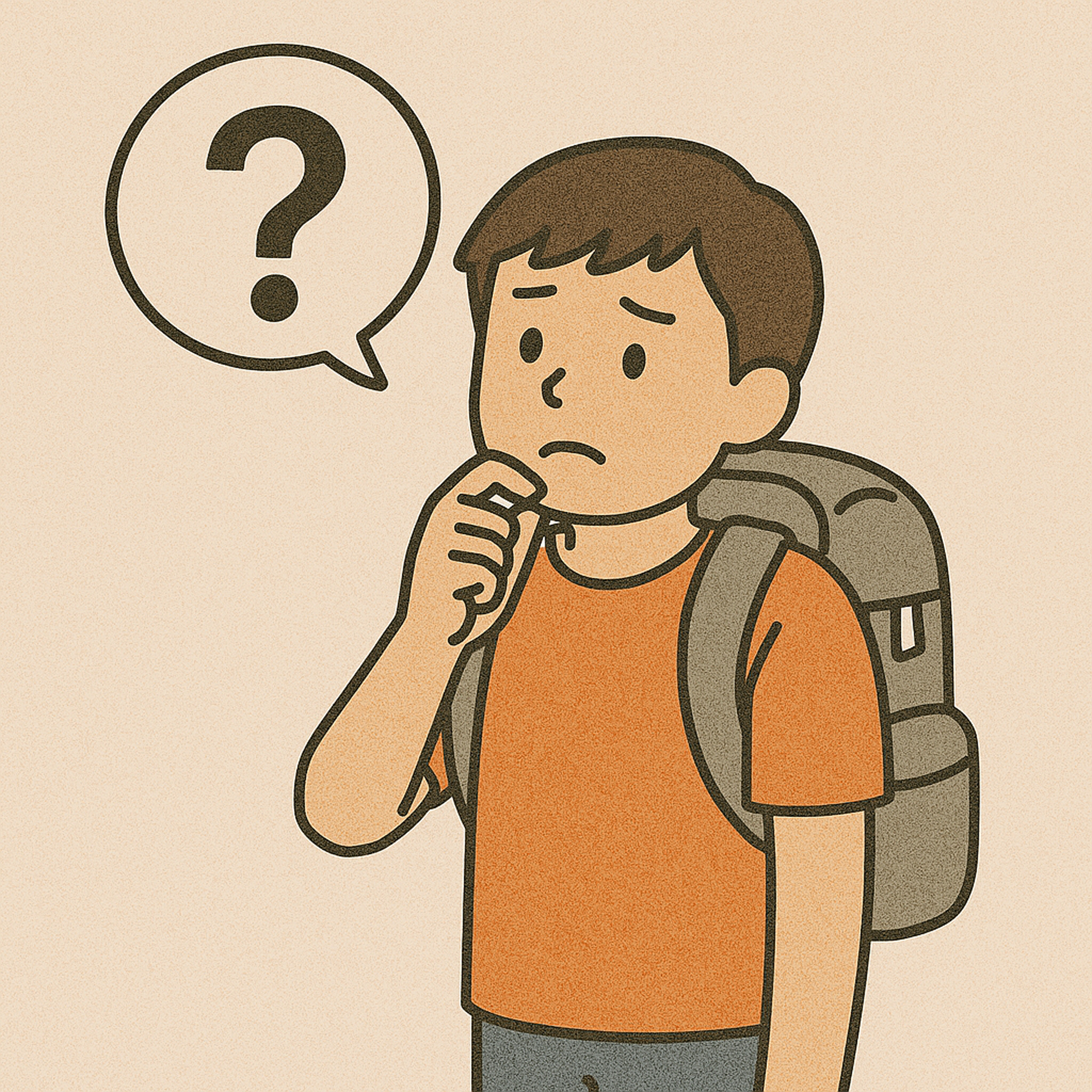 防災もやらされてやるものではないのですが、国は災害発生後72時間は人命救助を優先すると定めています。
防災もやらされてやるものではないのですが、国は災害発生後72時間は人命救助を優先すると定めています。
つまりこういうことです:
「3日間、生き延びた人は自力で頑張れ!」
生き延びるには、水や食料も大切ですが、「どうしたら?」という考える力が必要になります。
「まだ小学生だから」ではなく、
「小学生だからこそ」一緒に考えるべきなのです。
それが子供を強くすると信じ子供と向かい合っています。



コメント